設備職T.K.

経歴
| (大阪府水道部) 1994年 第一建設事業所 1996年 北部水道事業所 1999年 財団法人大阪府水道サービス公社へ出向 2001年 事業管理室 2004年 庭窪浄水場 2007年 事業管理室(主査級に昇任) 2010年 村野浄水場 |
(大阪広域水道企業団) 2011年 村野浄水場 2012年 南部水道事業所 2013年 神奈川県域広域水道企業団へ出向 2014年 南部水道事業所 2015年 事業推進課(課長補佐級に昇任) 2018年 北部水道事業所 2020年 庭窪浄水場 2022年 大阪狭山水道センター所長(課長級に昇任) 2024年 北部水道事業所長 |
これまでのあゆみ
1年目
採用後、阪神淡路大震災を経験し責任の重さを感じる
採用されてすぐに、池田市や島本町向けの送水管と三島浄水場への高度浄水施設を建設する部署に配属になりました。
当時は高度経済成長による琵琶湖や淀川の水質悪化とその結果として「まずい水道水」が問題化しており、「安全でおいしい水道水」を目指して、従来の浄水処理に加えて高度浄水処理の導入が進められていました。
いきなりその建設担当の一人となりましたが、右も左もわからず、仕事の進め方に苦闘していた時期に阪神・淡路大震災が発生しました。災害復旧の応援メンバーの一人として西宮市に派遣されたものの、できたことは漏水修理工事を監督する先輩職員を現場へ連れて行く運転手役でしたが、修理が完了して再び水道水が蛇口から出たときに受けた、住民からの感謝の言葉はライフラインを支える一員としての喜びと責任の重さを実感しました。
6年目
トラブルが続発するも、周囲に助けられ自身も奮闘する日々
水道事業の補完的業務を行う外郭団体へ出向しました。そこでは、電源の二重化と省エネルギー対策として、村野浄水場へ電力と熱エネルギーを供給するために、都市ガスを燃料とするコージェネレーション発電施設の建設業務の担当になりました。
稼働時期を守るためのタイトな工程の中、しゅん工が近づくにつれ連日連夜の突貫工事でしたが、その影響か試運転ではトラブルが続発していました。発電施設の責任者である主任技術者に選任されていたことからも、不安な日々を過ごしましたが、上司や同僚の助けを受け、また担当課の職員共通の目標に向かって奮闘した甲斐もあって、何とか工期に間に合うことができ、チームで結果を出す喜びや達成感を得ることができました。
14年目
主査に昇任し、より責任感を持って仕事に取り組む
この年、主査に昇任し、本庁の技術・危機管理グループに配属になりました。ここでは、設備系の新技術導入や工事の際の基準作りなどを行う技術管理業務に加え、災害対応に備えた訓練実施などの危機管理業務を担当しました。
当時、大阪市との間で広く事業連携していく方針の下、共同でCMの製作や訓練を実施することとなり、訓練担当者として大阪市の担当者と折衝を重ねて大阪市の導水管から村野浄水場へ原水を応援融通する訓練を実施しました。当日は双方の幹部職員に加えて、地元選出などの議員にも立ち会いをいただいており、業界新聞にも大きく扱われたことが思い出です。
20年目
他団体への派遣を経て、知見を広げる
神奈川県横浜市などに水道用水を供給する神奈川県内広域水道企業団へ1年間出向しました。浄水場の施設管理担当主幹として施設改良や維持運用の業務に従事しましたが、電気設備の保安に関する資格を有していたことから、その責任者に指名されたり、効率的な凝集・沈殿処理のためにメーカーと共同研究を実施することになり、その主担者として大半の業務を任されたりしました。他の事業体とでは仕事の進め方や考え方が違うことも多く戸惑うこともありましたが、これまでの経験を踏まえて何とか業務をこなしました。その経験のおかげか、複眼的なものの見方をできるようにもなったと思います。
26年目
再び地震災害を経験し、強靭な水道へ思いを新たに
淀川以北のエリアで送配水管やポンプ場などを管理する北部水道事業所の送水課長の時代に、大阪府北部地震が発生しました。吹田市にある職場で激しい揺れに恐怖を感じたのも束の間、次々に飛び込んでくる漏水をはじめとした施設の被災情報を整理し、鉄道が停止するなか少しずつ参集してくる職員を順次現場へ派遣し、現地からの情報を受けて対応を検討しさらに指示を出すといった作業が翌朝まで続きました。企業団の水道用水供給事業は受水団体である市町村へ水を送る役割を担っているため、この水が止まることは広範囲の断水につながる恐れがありました。
結果として多くの施設が被災して一部の地域では断水を余儀なくされましたが、職員一丸となって早期の復旧に向けて全力を尽くし、また受水団体の協力もあって翌日には解消することができました。その後も数か月間は地震が原因と考えられる漏水事故などが続発し、その対応に追われ落ち着く暇もありませんでしたが、阪神淡路大震災以来のこの経験がハード・ソフト両面について地震への備えの重要性にあらためて気付かされました。
29年目
より広い視野で水道事業に携わる
この年、大阪狭山水道センターの所長に就任しました。
大阪狭山水道センターは大阪狭山市内を給水区域とし、各家庭や学校などへ水道水を直接届ける役割を担っており、令和3年に大阪狭山市から企業団の事業として移管・設置されました。水道センターはこれまで携わってきた水道用水供給事業と違ってユーザーである一人一人の市民の声が直に届く職場です。
初めての職場でかつ大きな責任を伴う立場ですが、経営面も含めた事業全般に関われることにやりがいを感じています。これからも、施設のさらなる耐震化や安定的な経営の確保など解決すべき課題はありますが、企業団への統合効果を最大限発揮するめに全力を尽くしていきたいと思っています。
企業団への就職を考えている方へ
当企業団における機械・電気技術系職員の業務は、水道プラントの建設、維持更新や運用に留まらずユーザー対応なども担っています。24時間365日絶え間なく水道水を供給することが当たり前に要求される環境下で、専門知識、豊富な経験や蓄積されたノウハウに裏打ちされたプロフェッショナルの集団による組織力を発揮して、より安定性の高い水道プラントを構築・稼働させており、国内でも有数の大規模かつ複雑な制御方式の機械をコントロールする仕事には大きなやりがいを感じられます。
令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、改めて水道水の重要性がクローズアップされており、私を含め職員一同、ライフラインをあずかる者としての矜持と使命感で、その責任を果たすために日々力を注いでいます。
水道の将来は、人口減少や地震をはじめとした災害対策が大きな課題で、その解決のためにPPPやDXのさらなる推進など、前例にとらわれない考え方で取り組んでいくことが求められています。今回紹介した業務はほんの一例で、オンライン説明会のほかインターンシップや施設見学会も実施しておりますので、ぜひ、当企業団職員の話を聞いてみてください。一緒に仕事することを楽しみにしています。
お問合せ先
総務課 人事グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル3階
電話:06-6944-6046
ファックス:06-6944-6868









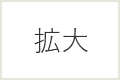




更新日:2025年01月06日